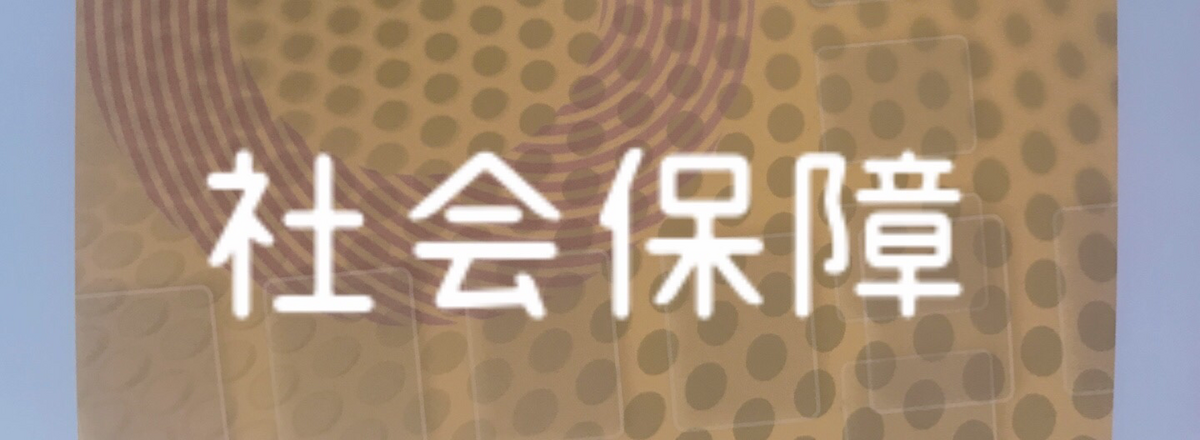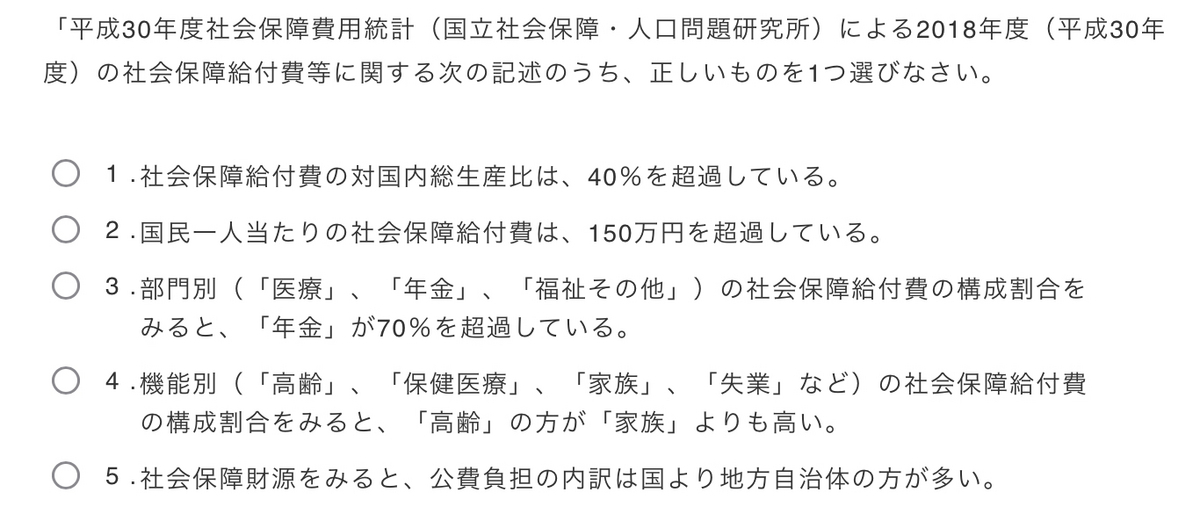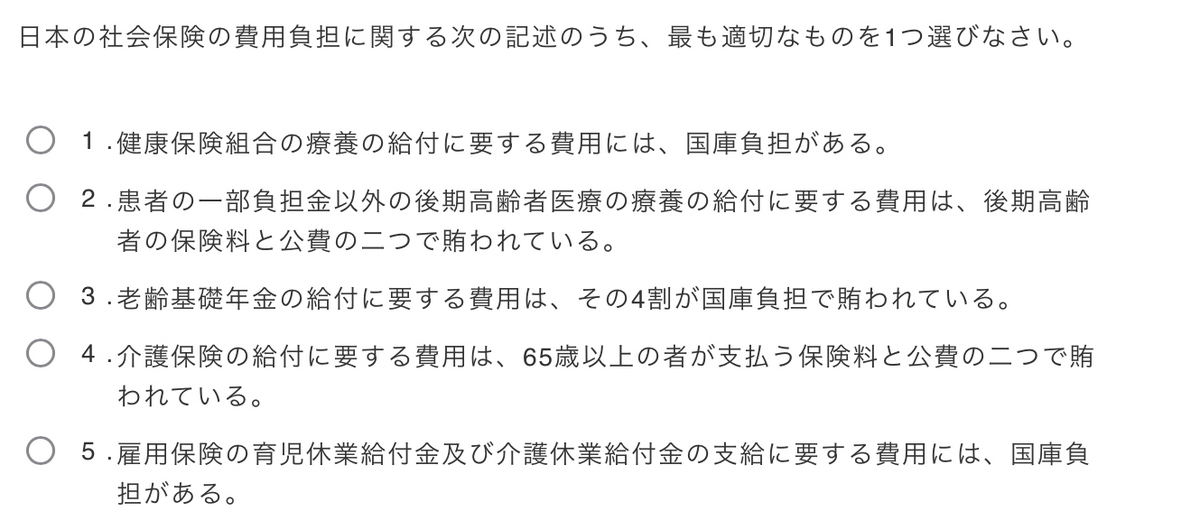😊よかったところ
最初から全力で走るのではなく、毎月の進度をみて、その都度調整していけたので、必要な力を入れることができた。
最初は何が大事で、何が発展的な内容なのか、全く掴めなかったが、やってるうちに、よく出るところが分かってきて、濃淡をつけて集中的に勉強することができた。
日常の中に勉強時間を組み込んで、戦時体制を取らなくても、平常のまま取り組むことができた。何かを諦めたこともなく、ストレスを溜めずにできた。
模試を利用して、直前に一気に覚える作戦が功を奏した。集中力や、モチベーションの高まりをうまく活用することができた。
本など、ほかの教材を効果的に使えたのがよかった。
独りよがりにならず、仲間を巻き込んで勉強できた。
🤔改善できるところ
毎日バランスよく勉強してきたけど、最後にやった、1教科を集中的に解いていく方法だと、より、よく出るところがわかりやすく、すぐに復習ができるので、知識の定着が早い。
問題が解ける→自分の言葉で説明できる→引っかけられるところがわかる、の最後の段階まで、もっと早くに引き上げておくべきだった。あまり早くからする必要はないけど、1月くらいにはこの段階に入りたかった。もう少し、早くギアアップしたかった。
ネットに書き込むより、紙ベースで、付箋に書いて貼った方が、最後にまとめて見るのに見やすい。パソコンで早く入力することと、上手く平行させたかった。
全体塗りを何度も、は良かったが、優先順位をつけて集中して塗りつぶしていけるとよかった。